 |
|
日本橋(朝之景) |
|
京都まで126里半東海道五十三次の起点、橋の手前5〜6人の魚屋が早朝の魚市から買い求めた魚をかつぎ、橋の上を大名行列の先頭が渡ってくる。あわただしい朝の日本橋界隈の情景が描かれている。 |
|
|
|
 |
|
品川(日之出) |
|
行列の最後尾と早朝店を開いている宿場外れの茶店と女達そして明け 始めた。品川沖から鮫州沖の海と茜色に染まった空が描かれている。 |
|
|
|
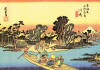 |
|
川崎(六郷渡舟) |
|
元和九年(1623)、徳川家康の宿駅制度制定から22年後に制定、川崎宿は品川宿、神奈川宿の伝馬百姓の負担を軽減するために設置された四村の集落で、本陣がなく、農村とあまり変らない宿場町として誕生しました。 |
|
|
|
 |
|
神奈川(台之景) |
|
家数1300軒、人口6000人、日本橋から三番目の宿場町であり、日本橋からは七里ほどで、一日で往復できる距離にありました。慶長六年(1601年)に伝馬の制が制定された。 |
|
|
|
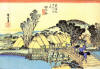 |
|
保土ヶ谷(新町橋) |
|
江戸を出発した大名行列や、戸塚までたどりつくのが困難な人たちの最初の宿泊地でした。70数件もの旅篭で活気があり、道中奉行の命令により街道は常に整備されていた。 |
|
|
|
 |
|
戸 塚(元町別道) |
|
旅人が馬から勢いよく飛び降りようとしている姿が巧みに絵になっています。鎌倉方面への分岐点とわかる「左り かまくら道」の道標が橋の手前にあります。江戸を出発した旅人にとって最初の宿泊地となりました |
|
|
|
 |
|
藤 澤(遊行寺) |
|
大鋸橋とその下を流れる境川を描いています。鳥居は、藤沢宿から江の島参りに向かう「江の島道」の入口を表わす第一鳥居です。後の石段をもつ寺は、時宗の大本山遊行寺です。大山詣で賑わう街道 |
|
|
|
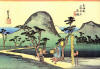 |
|
平 塚(縄手道) |
|
平塚宿には、平塚宿による西組問屋場と、平塚新宿による東組問屋場があり、本陣・脇本陣のほかに約五十軒の旅籠屋がありましたが、宿泊よりも休憩に利用されることの多い宿場だったようです。 |
|
|
|
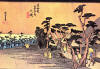 |
|
大 磯(虎ヶ雨) |
|
日本橋から8番目の宿場で、大磯宿までの間は約66kmで、もし徒歩ならば約16時間ほどかかることになります。大磯宿は、平塚宿と小田原宿の間が東海道でも有数の近距離になるため宿泊者が少なかったようで |
|
|
|
 |
|
小田原(酒匂川) |
|
領主の居城を中心に整備され東海道沿いには町屋が集中し、宿場町としての特有な町割となってます。
また、諸大名や幕府役人などが宿泊した本陣と、大名家の家臣が宿泊した脇本陣が各々四軒ずつありました |
|
|
|
 |
|
箱 根(湖水図) |
|
箱根西坂道は道幅は2間(3.6m)で両脇には峠より山中新田まで杉、ここより三島宿間は松が植えられ、三箇所に一里塚が設けられ道には石が敷かれていた。 |
|
|
|
 |
|
三 島(朝霧) |
|
1942年の記録では、家数1200軒、人口4048人。宿内の小浜池等には富士山の地下水が湧き出し、それが小川となって宿場内を流れていた。 |
|
|
|
 |
|
沼 津(黄昏) |
|
家数1234軒、人口5346人(1942年の記録)。宿内には橋がなく川を船で渡っていた、港町として栄え、遊興の町並みも開けていたといわれている。 |
|
|
|
 |
|
原(朝之富士) |
家数398軒、人口1939人(1942年の記録)。
原という地名は、この地に接した浮島沼がつくり出した浮き島ヶ原に由来する。海辺であるため漁業も盛んであった。 |
|
|
|
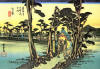 |
|
吉 原(左富士) |
|
(左富士)東海道を京に上る旅人は富士山を右手に見て旅をしているが、ここ吉原宿の手前の松並木から左に富士山が見えることにより「左富士」と呼ばれている。 |
|
|
|
 |
|
蒲 原(夜之雪) |
家数509軒、人口2480人(1942年の記録)。富士川の舟運で米や塩の輸送基地として栄えた。榊原ともいわれます。
|
|
|
|
 |
|
由 井(由比) |
|
家数160軒、人口713人(1942年の記録)。製塩なども行われたのどかな農漁村。現在も本陣をはじめ、往時の建築様式をとどめる民家もある。 |
|
|
|
 |
|
興 津(興津川) |
|
家数316軒、人口1668人(1942年の記録)。由比宿との間には難所で知られた薩埵峠があり、旅人にとっては重要な宿であった。 |
|
|
|
 |
|
江 尻(三保遠望) |
|
巴川のほとりに発達した江尻は清水次郎長でもおなじみの清水港にも隣接し、川や海を利用した交通が盛んだったところ。 |
|
|
|
 |
|
府 中(安倍川) |
|
家数3,673軒、人口14,071人(1942年の記録)。現在の静岡市に当たる。駿府の国の政治の中心地であったことから府中と言われた。古代から政治の中心地であった。 |
|
|
|
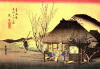 |
|
丸 子(名物茶店) |
家数211軒、人口795人(1942年の記録)。
現在でもとろろ汁が名物の丸子宿は、安部川の川越を扱い、川越人足が多くいた。宿の東口の見付けには古い民家が見られる。 |
|
|
|
 |
|
岡 部(宇津之谷峠) |
|
家数487軒、人口2322人(1942年の記録)。道は平安の古道である蔦の細道と、秀吉が開いた東海道に分かれる。 |
|
|
|
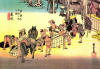 |
|
藤 枝(人馬継立) |
|
家数1611軒、人口4425人(1942年の記録)。田中城を仰ぐ田中藩の城下町。相良に通じる田沼街道、高根白山神社への参道高根街道、瀬戸谷街道など交通の要所であった。 |
|
|
|
 |
|
嶋 田(大井川駿岸) |
|
家数1461軒、人口6727人(1942年の記録)。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川、明治になるまで橋や渡船もなかった、毎回洪水を起こした大井川は難所であった。 |
|
|
|
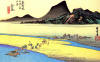 |
|
金 谷(大井川遠岸) |
|
家数1004軒、人口4271人(1942年の記録)。金谷本宿と、加宿河原町の二つによって成り立ち、大井川境から牧の原境まで達していた。 |
|
|
|
 |
|
日 坂(佐夜ノ中山) |
|
家数168軒、人口750人(1942年の記録)。徳川幕府直轄として代官支配下に置かれ、日坂宿の特徴となっている防火用の空き地が数多く整えられた。 |
|
|
|
 |
|
掛 川(秋葉山遠望) |
|
家数960軒、人口3443人(1942年の記録)。掛川の名産は葛布。秋の七草の一つである葛の繊維で織り上げる。古くは鎌倉時代から作られた、袴や裃の生地にも使われた。 |
|
|
|